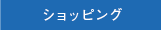- * 2022年度に張心治初段が姉、張心澄初段に続いて入段し、6月30日、初手合に挑んだ。心治初段は曾祖父に木谷實九段、祖父に小林光一名誉棋聖、祖母に小林禮子七段、父に張栩九段、母に小林泉美七段を持つ。4代にわたって碁の道に入った背景は何か、世代を超えて共有する碁の魅力は何か。心治初段の入段を期に、4代目棋士を世に送り出した3代目、小林泉美七段の「思い」を聞いた。
「思索する人の最も美しい幸せは、究め得る道を究め、究め得ないものを静かに尊敬するにある」。小林禮子七段が気に入っていたゲーテの一節だ。「私も好きです」。古い雑誌に書いてあるこの一文を見せながら小林泉美七段が言う。祖父、木谷實九段の代から続く碁を打つ喜び、それは一生かけても究め得ないことに取り組むという探求の喜びだ。
泉美の祖父、木谷九段(1909年―1975年)は呉清源九段と共に一時代を築いた大棋士だ。「祖父は常に全身全霊で対局に臨み、それこそ命を削って道を究めようとした人でした」。空気と同じように碁を欲し、脳溢血で倒れてもなお、医師同伴で碁盤の前に座り打ち続けたという。
泉美が誕生する2年前に故人となり、直接会うことはできなかった。しかし母、禮子七段(1939年―1996年)は父を非常に尊敬していて、その生き様や精神性をよく語ってくれたという。「盤上は神聖なもの。手合は絶対的なもの。母の考え方は完全に祖父を受け継いだものでした」。木谷九段は盤上を離れるとお茶目で面白い人だったそうだが、禮子七段もまたユーモアのある人だった。「祖父はよくダジャレを言っていたそうですが、母もよく言っていました(笑)。」棋士として、人として、父を敬愛していた禮子七段はそんなところも木谷九段にそっくりだった。
木谷九段の弟子で泉美の父、小林光一名誉棋聖もまた、木谷九段の碁に対する姿勢を色濃く受け継いでいる。「私は毎朝父が棋譜並べをしている音で目を覚ましていました。本当にどんな時にも碁に向き合っている人だと思います」。
両親ともに碁に人生を捧げていたが、求道者のような雰囲気のある母に比べて、父、光一名誉棋聖は野心的で、頂点に立つことを目指していたように感じる。「母の打ち方はあまりにも没頭していて怖いくらいだったので、父は口にこそ出さなかったですけど、もう少し気楽に打てばいいのに、と思っていたのではないかと思います。でもそれは父が没頭していなかったということではありません。本当に研究量がものすごくて、常に努力していました」。
道を究めることと勝負に勝とうとすることは全く同じことだと泉美はいう。「父は確かに勝つことを重視していたと思いますが、もちろん碁そのものを究めるつもりだったと思いますよ」。
泉美は碁が中心の家庭の中で、自然と棋士の道を歩むことになった。「『プロになりなさい』とか『碁の勉強をしなさい』とは一度も言われていないと思います。でも、母からは碁をやってほしいのだろうなと感じるものはありました」。禮子七段は癌のために泉美が18歳の時に亡くなってしまう。「晩年、母は『碁は5につながる。だから5代で一局なのよ』と言っていました。私がまだ3代目なのに随分気が早いな、と思っていたのですが、叔父たちに聞いたら、『5代棋士を続ける』というのは祖父が言っていたことだったそうです」。代々碁をつないでいくというのは木谷九段から禮子七段に引き継がれた願いだったのだ。
泉美が伴侶に選んだ張栩九段もまた、祖父、母、父に負けず劣らず碁に人生を捧げている人だ。張九段は木谷九段の盟友である呉九段の孫弟子。運命的なものを感じざるを得ない。
張九段は知的好奇心の塊のような人で、それが泉美には新鮮に映った。「私にとって碁は取り組むべきことで碁の勉強は勉強でした。でも、張栩はすごく楽しそうで、ああ、碁って面白い、楽しいことなんだな、と改めて気づかせてもらった気がします」。
張九段の詰碁はいつも遊びの延長で生まれている。1路違うだけで、手順を少し変えるだけで、見える世界が全然違う。碁の可能性を開拓していく面白さ。「碁は神聖なもの」という母の考え方を受け継いでいた泉美に、張九段の姿勢は、碁をゲームとして楽しむという新しい視点を与えてくれた。
2020年に長女の張心澄初段(16歳)が2022年に次女の張心治初段(12歳)がプロ入りした。泉美は「二人が健やかに育って、碁を好きになってくれて嬉しい」と話す。「一家で同じものを共有できているというのはすごく幸せなことです。同じように取り組んでいることだから、そこに至るまでの努力を理解できるし、悩んでいることもおもんぱかれる。父と娘が打っている姿を見ても、碁を通じて深いところで理解し合えているなと感じます。世代が違っても分かり合える関係を築けているのは碁のおかげです」。
共通の課題であり、夢であり、コミュニケーションツール。張家では家族でよく打ち、よく語る。「私は父に打ってもらったことは数えるほどですが、母に打ってもらったことはもっと少なくて、ほとんどありません。それだけは残念に思っているので、私は娘たちとたくさん打とうと思っています」。家族で勉強していると、楽しくて寝食を忘れてしまうほどだという。
「『思索する人の最も美しい幸せは、究め得る道を究め、究め得ないものを静かに尊敬するにある』この言葉で特に好きなのは後半部分です。たとえ自分で究められなくても、究めている人を尊敬はできますものね」。泉美自身も女流碁界の第一人者だった人だ。けれど、結婚後は母、禮子七段が光一名誉棋聖を支えたのと同じように、張九段を支えることに重きを置いた。前述の言葉は、なぜ泉美がそういう道を選んだのかを物語っているようだ。
碁は自分の勝ち負けや生活の糧以上の存在で、先祖代々家族で取り組むべき巨大プロジェクトなのだろう。「娘たちには二人で力を合わせて、自分達で道を切り拓いていってほしいです」。それぞれ究めえる道は違う。同じように碁に取り組んでいても、究め方はいろいろある。他の人の努力や成果に敬意を持って、自分も自分で見つけた方法で碁を究めていってほしい。それが母としての願いでもあるし、4代目を送り出した3代目の思いでもある。

泉美の対局を見守る光一名誉棋聖と禮子七段

木谷實九段と禮子初段(当時)。昭和32年初春・平塚海岸にて。